当サイトはアフィリエイト広告を利用しています(商品リンクにはPRを含む場合があります)。
こんにちは、庶民派ブロガーのピロです!
秋も深まり、そろそろメダカの繁殖シーズンも終わりに近づいてきましたね。「今年最後の卵かもしれない…!」と大切に見守っているのに、気づいたら卵や針子が消えている…そんな経験、ありませんか?
「昨日まで確かにあった卵が見当たらない…」
「孵化したはずの針子が数日で半分以下に…」
「これって親メダカの共食い?それとも死んでしまった?」
実は僕も、シーズン最後の貴重な卵を「気づいたら全滅」させてしまった苦い経験があります。その時は「親メダカが食べちゃったのかな…」と諦めていましたが、後から調べて分かったのは、原因は一つじゃなかったということ。共食いだけでなく、様々な要因が複雑に絡み合っています。まずは、その「犯人」を特定しましょう!
今回は、メダカの卵・針子が消える「本当の原因」を徹底解剖し、シーズン最後の貴重な命を守るための具体的な対策をお伝えします!
この記事を読めば、あなたの大切な卵と針子を無事に育て上げるヒントが必ず見つかるはずです。
症状の切り分け早見表
- 卵が消えた
- 無精卵が白濁 → 崩壊
- 親・巻貝・エビ等の捕食
- 水換えや掃除で誤吸い出し
- 低水温で発生停止 → カビ化
- 強い水流で産卵床から脱落
- 針子が消えた
- 親/先輩稚魚の捕食(共食い)
- フィルター吸い込み
- 表面皮膜(油膜)で初回の空気取り失敗
- 低水温・酸欠・過密
- 飢餓(餌サイズ/頻度ミスマッチ)
- 屋外の天敵(水生昆虫・ヤゴ等)
- アンモニア/亜硝酸ショック
卵が消える原因と対策
1) 無精卵・カビ化で“溶ける”
- サイン
- 乳白色・白濁、綿状のカビ(他の卵へ伝播)
- 季節末ポイント
- 低温・短日で受精率が低下、発生が止まる
- 対策
2) 親やタンクメイトの捕食(共食い)
- サイン
- 朝には産卵床から卵が激減、床材の端だけ残る
- 対策
- 産卵床を毎朝回収→別容器で卵管理
- 親とは“別管理”が鉄則。浮き巣だけはNG(食べやすい)
- エビ・巻貝でも卵をつつく種類あり(レッドラムズは卵狙うことあり)
[PR:産卵床]
3) 水換え・掃除での“誤吸い出し”
4) 低水温・短日による発生停止
5) 水流で脱落・行方不明
- サイン
- 外掛けや上部濾過の出水口直下で卵が見当たらない
- 対策
- 流量を弱め、出水を壁打ちに変更/ディフューザーで拡散
- 卵は低水流の別ケースで管理
[PR:コック付き分岐]
針子が消える原因と対策
1) 親/先輩稚魚の捕食(共食い)
- サイン
- 朝夕に数が減る、大小混泳で小さい方がいなくなる
- 対策
- 同サイズで分ける(“サイズ別水槽”は生存率を上げる近道)
- 隠れ家を密に(浮草の根、ウィローモス、カボンバ)
- 針子は専用ケースに隔離(掛け式サテライト or 小型育成水槽)
[PR:ブリーディングボックス][PR:水草/浮草セット]
2) フィルター吸い込み
- サイン
- 姿が見えず、ろ過槽内に稚魚
- 対策
- 吸水口にプレフィルター(スポンジ)を装着
- 針子期は“スポンジフィルター+弱エア”が基本
[PR:スポンジフィルター]
3) 表面皮膜で初回の“空気取り”失敗
- 解説
- 針子はふ化直後に水面で空気を取り込み、浮き袋を開く。油膜/タンパク膜があると窒息・沈みやすい
- 対策
4) 酸欠・過密
5) 低水温・摂餌不良
- サイン
- 口を使わない、痩せる、成長停滞
- 対策
- 針子育成は22〜26℃が安定(低すぎると餌反応が落ちる)
- 季節末は“育成だけ加温”が効率的(小水量×省電力ヒーター)
[PR:小型ヒーター]
6) 飢餓(餌サイズ/頻度ミスマッチ)
- 目安
- ふ化0〜3日:インフゾリア/ゾウリムシ/液体フード
- 3〜7日:超微粒子粉餌(0.1〜0.2mm)
- 7日〜:ブラインシュリンプ/微粒子+生餌MIX
- 対策
7) 屋外の天敵(水生昆虫・ヤゴ等)
- 対策
- 細目ネット/フタで侵入防止
- 水草をトリミングして見通しを良くし、天敵を発見しやすく
[PR:防虫ネット]
8) アンモニア/亜硝酸ショック
季節末(秋〜初冬)ならではの“卵と針子”運用のコツ
- 受精率が下がる前に「打ち止め」判断も大切
- 無理に越冬直前まで採卵せず、“親の体力温存”を優先する選択も◎
- どうしても増やすなら“局所加温”
- 卵・針子の小型ケースだけ24〜26℃、照明12〜14hで管理
- 親は18〜20℃の維持でもOK(繁殖は狙わない)
- ふ化日数の目安(管理計画に)
- 26℃:約7〜10日
- 24℃:約10〜14日
- 20℃:約14〜21日
- 18℃以下:大幅遅延〜停止(カビリスク増)
まとめ|“分ける・守る・温める・小さく与える”
- 卵は“毎朝回収して別管理”、無精卵/カビは即除去
- 針子は“サイズ別×低水流×隠れ家×弱エア”、油膜カット
- 季節末は“局所加温+長めの照明”で発生と摂餌を後押し
- 餌は“サイズ・頻度”を針子基準に、小さく多回で水を汚さない
「共食いかな…」で終わらせず、原因ごとに手を打てば“最後の一腹”の生存率は大きく伸びます。ぜひ今日から試してみてください!
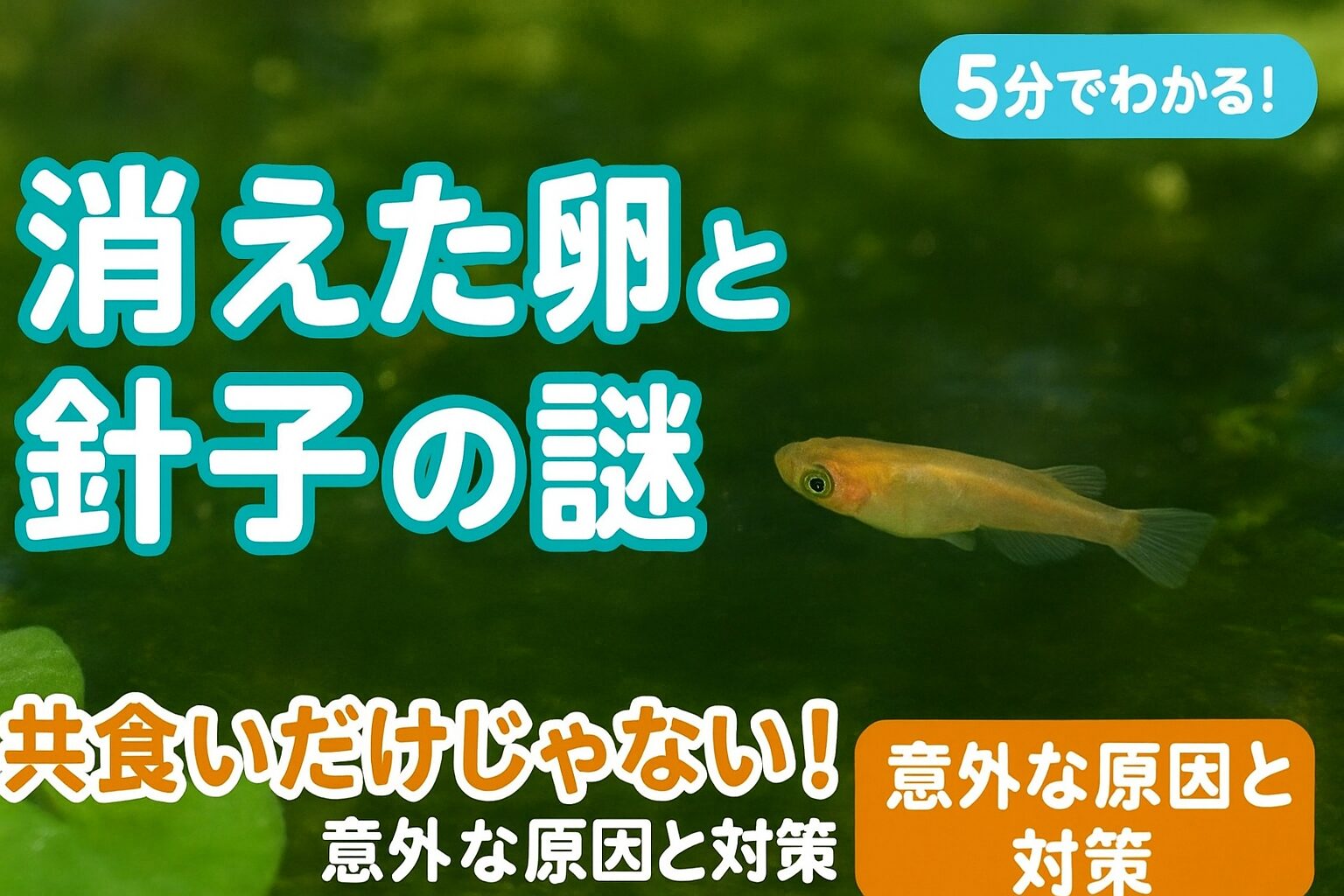
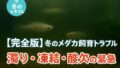

コメント